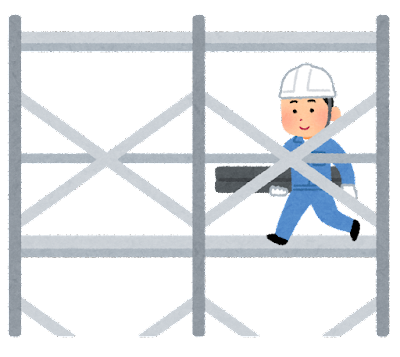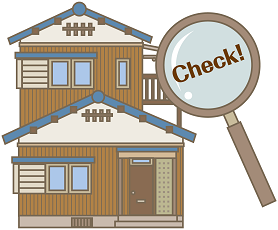リノベーション作業が始まる前に、既存の構造物や設備の解体が行われます。また、新しい設備や建材の配送や保管などの準備も行います。

建物の骨組み・構造を残して、内装を一新するようなリノベーションの場合、壁や床の取り外し、古い設備の撤去などを行います。同時に、新しい建材や設備の配送や保管についても計画していく必要があります。解体作業が進む中で、職人さんが安全に作業を行うため、また、建物や周囲の環境への影響を最小限に抑えるために、養生を施したり、足場を確保するなどの準備も行います。これには、建材の搬入経路の確保や保管場所の準備、必要な機器や道具の手配などが含まれます。
何事もそうですが、準備が万全であればその後の工事もスムーズに進みます。工務店の腕の見せ所は、現場監督の調整能力とも言えるのです。