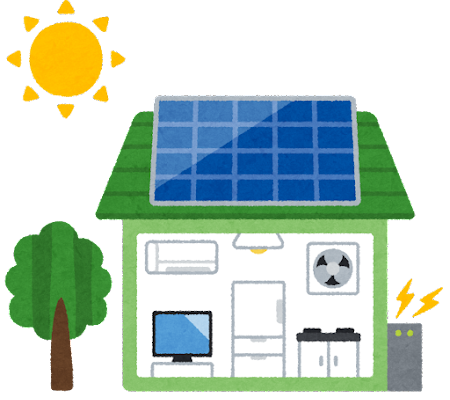大丸建設では国産の無垢材を使った家づくりをしています。第一次産業でもある林業は、昔ながらの職人技や目利きの力が必要な分野ではありますが、産業的には高齢化の波が押し寄せ、廃業をする林業家も少なくありません。

一方で、林業の世界にも最近のICT技術の進歩の時流に乗って、「スマート林業」なる言葉が少しずつ普及し始めています。林野庁では森林資源のデジタル化とスマート林業の推進を始めており、ICT技術を駆使して林業へ新規参入する若者も出てきています。
具体的には、レーザー技術を活用して森林資源のデータを解析したり、ICTを活用した林業生産管理システムを導入するなど、林業におけるさまざまな工程でICT化が進みつつあります。
林野庁では極力、統一した標準仕様書を作成し、日本全国で統一した基準で林業に関するデータを管理・共有できるような仕組みにしたいと考えているようです。