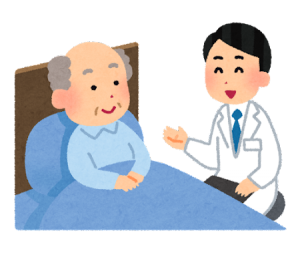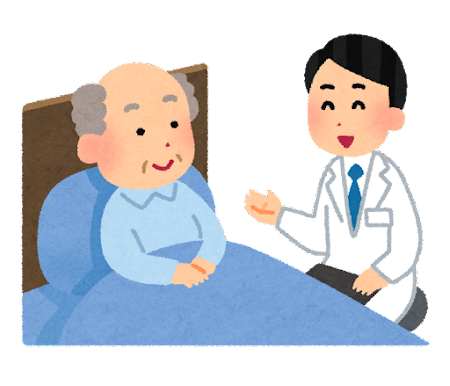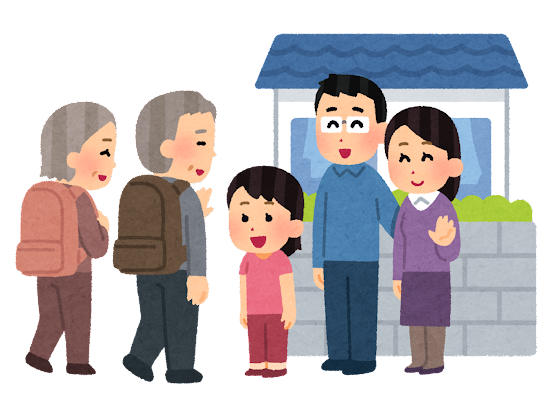今月は多様化したシニア向け住宅や介護サービスについてお話ししました。高齢になってからの住まいの選択肢は増えましたが、前提として考えたいのは、「愛着のある今の家に住み続ける」ためにどうしたらいいのか? ということです。
ご自身が心身ともに健康であることはもちろんですが、いつどのような状況で健康を損ねるかわかりませんし(突然の事故や転倒、病気などがあるかもしれません)、年齢を重ねれば誰もが体調にもアップダウンが出てくるのは自然なことです。そんな時に急激な環境変化が重なると負担も増えてしまいます。自分自身が「今の家に住み続けたい」と願えば叶うように、準備をしておくことも大切です。

高齢者の事故の多い段差をなるべく減らしてバリアフリーにする。手すりなどをつける。寒暖差をなるべく減らすなどの対策をすることで、愛着のある住まいに長く住み続けることができるようになります。
大丸建設では断熱対策やバリアフリー改修なども手がけていますので、ぜひお気軽にご相談ください。