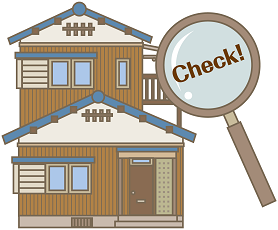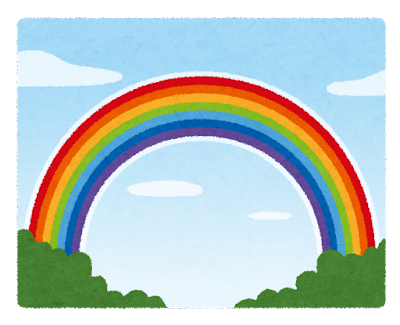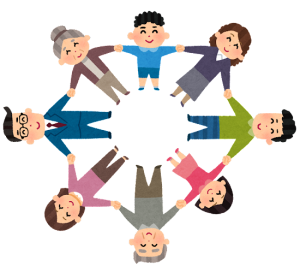リノベーション工事が完了したら、建物の検査が行われます。建築基準法の遵守や安全性の確認を行い、検査が合格したら、お客様に引き渡します。
リノベーションの場合、既存の構造と新しく追加される構造や内装が調和しているかを確認していく必要があります。新築住宅と比較して、既存の構造を考慮する必要があるため、より緻密なチェック、確認することが求められます。

住み始めていくなかで、不便なことがあったらすぐに工務店にご相談ください。これは新築住宅でも同じことですが、自然素材の特性で、木が割れるような音が鳴ったり、梅雨の時期は木が膨らんで建具の動きが変化するなどが起こることがあります。住み始めて数ヵ月は、いろんな変化が起こりますので、遠慮なく質問して、なるべくすぐに解決していけるようにしましょう。